スマート農業をはじめる!導入への課題と事例について紹介
近年、世界全体でICTの導入が進んでいます。その中でも、ICTを活用した農業は「スマート農業」と呼ばれ、農林水産省も積極的に導入を推奨しています。農業にICT技術を取り入れることで、どのような効果が得られるのでしょうか。
もちろん、スマート農業の導入にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。スマート農業の抱える課題を解決するにはどのような対応策があるでしょうか。
今回のコラムでは、スマート農業の概要やメリット・デメリット、実際にスマート農業を取り入れたお客様事例について解説します。
目次
スマート農業とは
スマート農業とは、ICT(情報通信技術)やロボット技術を活用し、農作業の効率化や農作物の品質向上を図る、次世代型の農業手法です。現在、日本全体ではICT化が進んでいますが、農業の分野では、いまだ人手に頼る作業が多く残っています。
加えて、農業従事者の高齢化や人手不足が深刻化しており、持続可能な農業経営の実現が課題となっています。こうした背景の中で、スマート農業は作業の効率化・省力化を実現するための手段として注目されています。
農林水産省も、農業分野の担い手の減少・高齢化の進行などによる労働力不足を深刻な問題として捉えており、スマート農業の普及に向け、さまざまな情報発信や支援策に取り組んでいます。
スマート農業の定義
農林水産省は、「スマート農業」を「ロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業」と定義しています。
このような農業について海外では、
・スマートアグリカルチャー(Smart Agriculture)
・スマートアグリ(Smart Agri)
・アグテック(AgTech)
・アグリテック(AgriTech)
などとも呼ばれており、日本よりも一足先にさまざまな国で導入されています。
スマート農業の主な取り組み

ICTとは、ITとほとんど同じような意味ですが、特にコンピューター技術の活用を強調する際に用いられます。
「スマート農業」をはじめとする政府の支援策や働きかけもあり、近年、農業にITを導入する事例が増加しています。
続いて、実際に生産現場に導入されている農業ITの導入事例について紹介していきます。
ロボット技術×農業
ロボット技術を活用したスマート農業では、収穫用ロボットや農薬散布用ドローン、無人トラクターなどが導入されています。
例えば、収穫用ロボットは、長時間や夜間の作業も行え、収穫時期の人手不足を補うことができます。さらに、AIなどで学習させることで作業の精度やスピードを改善できるのも大きなメリットです。
ビッグデータ×農業
データを解析することで、これまで把握できなかった栽培に関する情報を見える化できます。
長年蓄積された気象データ、土壌データ、収穫量データなどを分析することで、収穫時期の予測や勘に頼らない農業を実現できるようになります。
また、市場動向や消費者ニーズのデータを活用して、需要に合わせた生産計画を立てることも可能です。
データを活用するという意味では、体力的に自信のない人でも業務ができるので、幅広い人にも農業への門戸が広がります。
AI×農業
ChatGPTでも話題になっているAI技術は、農業においても活躍しています。
AIは、データ分析や意思決定を自動で行うため、画像解析や収量・出荷予測をすることができます。
例えば、画像解析AIを使って病害虫を見つけたり、最適な収穫のタイミングを把握したりするなど、過去のデータと気象予報を組み合わせて栽培計画を立てることに活用されています。
また、農作業のノウハウをAIに学習させることで、人件費削減だけでなく、精度の向上にもつながるため幅広く活用できます。
IoT×農業
家電や自動車にも活用されているIoTの通信技術は農業にも活かされています。
IoTを導入したスマート農業では、センサーやデバイスがネットワークでつながり、得られた情報をリアルタイムで確認することができます。
例えば、IoTの技術は田畑やハウス内の状況把握に役立てられています。
小型カメラとネットワークシステムを活用すれば、気温・湿度・雨量といった気象データと作物の育成データの把握が容易になります。
また、土壌センサーで水分や栄養状態をチェックしたり、自動灌水システムと連動させて最適な水やりをしたりするなど、農作物が育ちやすい環境を作ることができます。
スマート農業のメリット

ここまで紹介してきたような技術を導入することで、農業のやり方やそこで働く人たちの働き方も大きく変化するでしょう。
続いて、農業にIT技術を導入することで生まれるメリットについて紹介します。
省力化による圃場の拡大
農業にIT技術を取り入れることで、大幅な省力化が期待できます。
例えば、農地の状況を知りたければ、実際に圃場に行かずとも、ドローンやセンサーなどでチェックすれば、見回り回数を減らせるでしょう。
また、スマートフォンの通知機能と組み合わせることで、それまでよりも早く異常を知ることができます。
さらに、人が操作しなくても自動で作業可能なロボットの登場により、これまで人員的に広げられなかった圃場の規模を拡大することができるでしょう。
肉体への負担軽減
農業=きついというイメージは、スマート農業が本格的に導入されれば払拭されるでしょう。
自動運転農機や収穫ロボットなどによって一部の作業が削減されれば、体への負担も軽くなります。これらは、農家の高齢化や労働力不足という課題に大いに役立つと言われています。
農業技術のデータ化&活用
これまで個人の経験や勘に頼っていた農業のノウハウや技術をデータ化することで、農業未経験者でも一定の品質を保った農作業が可能になります。例えば、AIが作業の調整や予測、計画立案を担うことで、誰でも収益性の高い農業に取り組むことができます。
もちろん、人の手による作業が完全になくなるわけではありませんが、スマート農業の普及によって「きつい・汚い・危険」といった従来の農業に対するネガティブなイメージが払拭され、農業の働き方や産業としての魅力が大きく変わる可能性があります。
農薬使用量の削減
従来の慣行栽培では、収穫量の増加や作業負担の軽減を目的として、雑草や病害虫の防除に農薬が広く使用されてきました。しかし、環境負荷や人体への影響を考慮すると、農薬の使用は可能な限り抑えることが望まれます。
そこで、スマート農業の技術を活用することで、必要な場所にのみ、必要最小限の量の農薬を使用することができます。これにより、農薬の使用量削減だけでなく、農薬にかかるコストの削減も行うことができます。
スマート農業のデメリットと課題
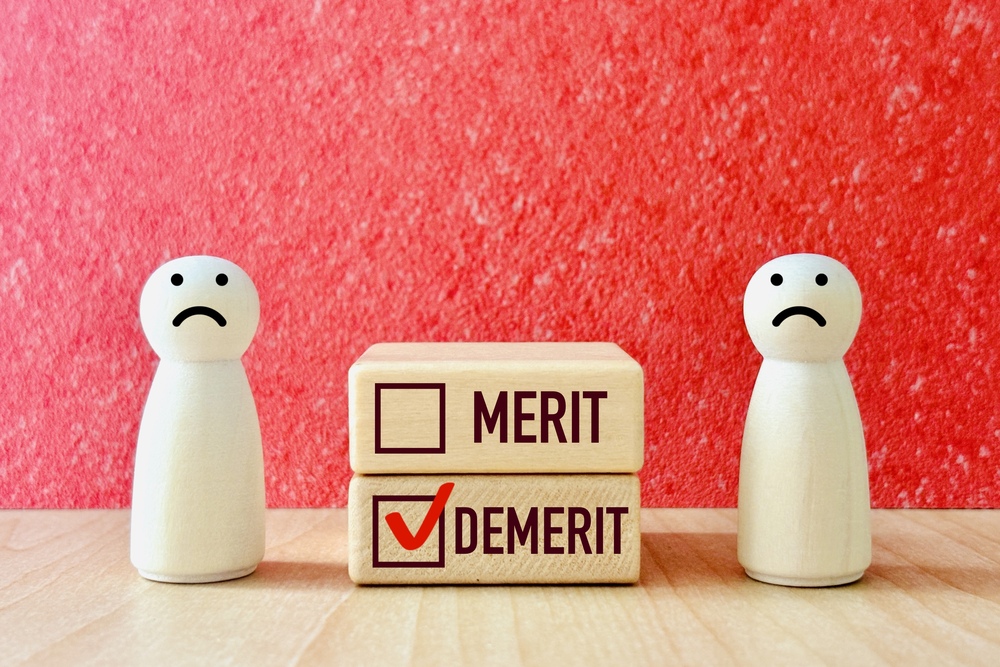
最新の技術を用いるスマート農業には、下記のようなデメリットや課題もあります。
高額な導入コスト
スマート農業の導入には、初期投資が従来の農機と比較して高額になる傾向があります。
また、仮に導入できたとしても、ICTやロボット技術の操作には一定のスキルが求められるため、現場の作業者の習熟度によっては十分な効果を発揮できないケースもあります。結果として、費用対効果が見込めず、導入後に運用を断念する農業経営者も少なくありません。
このように、スマート農業の導入には、コスト・人材育成・サポート体制といったさまざまな課題が存在します。
ソフトウェア形式の互換性
スマート農業に用いられるICT機器やロボットは、メーカーごとに独自の仕様や機能を持っているため、ソフトウェアやデータ形式の統一性に欠けるという課題があります。特に、農業関連データの管理・保存・移行に関しては、長期的な視点での運用設計が不可欠です。異なるシステム間で互換性がなければ、将来的な拡張や連携が困難になる可能性があります。
スマート農業の担い手不足と育成課題
農業従事者の高齢化が進む中、スマート農業の普及には「人材育成」という視点が不可欠です。
高齢の農業従事者にとって、ICT機器やロボットなどのスマートデバイスを使いこなすことは容易ではなく、導入後の運用に課題が残るケースも少なくありません。
そのため、スマート農業製品の操作支援や導入後のフォロー体制の整備、さらにはITリテラシーを持つ人材の育成が、農業分野における課題となっています。
新たな作業負担
スマート農業の導入によって、農業経営者側にも金銭的・時間的・技術的な負担が生じます。従来の農機導入と比較して、操作や管理に関する知識・スキルの習得が求められる場面が多く、導入のハードルは決して低くありません。
農作物本来のおいしさへの追及
作業効率や収量の向上が期待される一方で、忘れてはならないのが「農作物の味」という本質的な価値です。いかに生産性が高くても、消費者が選ぶのは“おいしい”農作物であり、品質の高さが市場競争力を左右します。
例えば、オランダの植物工場のように、安定した収量を確保する取り組みは重要ですが、人工光によって育てられた野菜は、太陽光を十分に浴びて育った露地栽培の野菜と比較すると、味の面で劣ると指摘されることもあります。
スマート農業は、あくまで「おいしく、栄養価の高い農作物を育てるための手段」であり、目的そのものではありません。技術の導入によって作業負担を軽減することは重要ですが、最終的なゴールは消費者に選ばれる品質の高い農産物を作ることです。
スマート農業導入の課題を解決する方法
上記で説明したデメリットや課題には、時間のかかる内容もありますが、個人の情報取集や取り組みによって改善できることもあります。
例えば、導入コストの解決方法として、補助金や助成金の活用が挙げられます。補助金や助成金制度を利用することで、金銭的な負担を減らしてスマート農業を実施することにつながります。
また、スマート農業に必要なコストを抑えるためには、リース・レンタルの活用も有効です。購入によりすべての費用を払うわけではなく、利用している一定期間の料金だけを支払うことで、高額な費用負担を避けることができます。
また、近年レンタルではなく、シェアリングする取り組みも行われています。近隣の農家同士でシェアリングできれば機械のコストを抑えることが可能になるため、一般での普及が期待されています。
補助金を活用してスマート農業を導入しよう

スマート農業は農林水産省が推進しており、さまざまな補助金を通じて普及を後押ししています。金銭的な負担を抑えることで、より多くの農業従事者が先進技術を導入しやすくなります。
補助金の目的
スマート農業の補助金には、以下のような目的があります。
・農業の生産性向上と省力化を促進すること
高齢化が進む中、限られた人員でも効率よく作業を進めることが期待されています。
・若者や新規就農者の参入を促すこと
3K(キツい・汚い・危険)のようなイメージを抱かれがちだった農業を、先端技術の活用や新しいアイデアによって払拭します。
・農業の競争力強化を図ること
スマート農業で農産物の品質アップや安定生産を実現します。
補助金の申請方法
補助金の申請方法は以下のフローで行います。
① 農林水産省のホームページから公募要領を確認する
② 申請書類を作成する
③ 必要に応じて各補助金の問い合わせ先に相談・確認を行う
④ 申請書類を提出し、審査結果を待つ
まず、農林水産省のホームページで最新の公募情報をチェックし、
詳しい要件や提出書類を把握します。
次に、事業計画や必要書類をミスなく作成します。
不明点がある場合は、補助金ごとの問い合わせ先に確認しながら作成を行います。
書類作成後は、期限内に正確に提出します。
その後、審査結果を待ち、採択されれば事業を開始できます。
イノチオのスマート農業製品
イノチオアグリでは、さまざまなスマート農業製品をご紹介しております。
環境制御システム AERO BEAT(エアロビート)

イノチオアグリの環境制御システム「エアロビート」は、ビニールハウス内外の状況を各種センサが感知し、自動で細やかな制御をおこなってくれます。本体とコンピュータ1台で最大10区画または、ハウスを最大10棟まで遠隔で管理することができます。人の経験や勘ではなく、データに基づいた農業をサポートしてくれます。
必要な機能だけを備えた「エアロビートmini」も新たに登場し、栽培規模に合わせて3つのラインナップ(制御点数:8点/16点/24点)から最適な製品を選ぶことができます。
製品情報:環境制御システム AERO BEAT(エアロビート)
製品情報:環境制御システム AERO BEAT mini(エアロビートミニ)
自動灌水制御システム AQUA BEAT(アクアビート)

自動灌水制御システム「アクアビート」は、時間制御・流量制御・液肥倍率制御による多様な灌水が可能です。特に流量制御による1株あたりの設定は、マニュアル化や異なるハウス間での管理、部会などでの情報共有に役立ちます。
最新の「アクアビートメビウス」では、AI学習機能を搭載しており、より精度の高い灌水管理を実現できます。
製品情報:自動灌水制御システム AQUA BEAT(アクアビート)/AQUA BEAT MOBIUS(アクアビートメビウス)
培地重量センサ スラブサイト

培地重量センサ「スラブサイト」は、培地内の水分量を見える化し、適切な灌水管理をサポートします。培地重量を常に計測し、PCにグラフで表示することで、培地内水分の変化をリアルタイムでモニタリングすることができ、農作物の収量や品質の向上につながります。
労務管理システム agri-board(アグリボード)
「agri-board」は、施設園芸の労務管理・目標管理から「ムリ」「ムラ」「ムダ」をなくし、作業進捗を「視える化」します。
タブレットでの作業の進捗入力と収穫量の実績入力により、誤記入を防ぎ正確な作業データを取得することができます。また、リアルタイムで労務管理者が進捗入力を閲覧することげできるため、管理コストの軽減につながり、管理者の労働効率も向上します。
製品情報:労務管理システム agri-board(アグリボード)
スマート農業技術を活用したお客様
農業のIT技術を活用して生産に取り組んでいるイノチオのお客さま事例を紹介します。
山田裕也さん

愛知県豊川市で「スプレーマム」の栽培を行う山田裕也さん。栽培面積は約2,400坪で、ハウスは10棟ほど使用しています。
山田さんは、イノチオアグリの環境制御システム「エアロビート」を導入しています。
本来であれば1つのハウスに対し1台機器を入れますが、エアロビートは1台で複数のハウスを管理できます。そのため、コスト削減や作業の効率化に役立っています。
また、温度や湿度の細かな管理が可能なため、作物にとって最適な環境を維持しやすく、品質の向上につながることが期待できます。
山田裕也さんのハウス導入設備や栽培への想いについては、こちらの動画でさらに詳しくご覧いただけます。
事例動画:環境制御システムを使用したスプレーマム栽培 山田裕也さん
スマート農業の相談はイノチオアグリへ!
ビニールハウスにたずさわり50年以上の歴史を持つイノチオアグリは、「農業総合支援企業」として数多くお客さまをご支援してきました。
イノチオアグリでは、ビニールハウス建設や農業ITに関連した製品だけでなく、収支シミュレーションに基づく作物や栽培方法のご提案や各種資材の提供まで、お客さま一人ひとりの状況に合わせて総合的にサポートさせていただきます。
農業に関するお悩みは、ぜひイノチオアグリにご相談ください。
